Blog ブログ
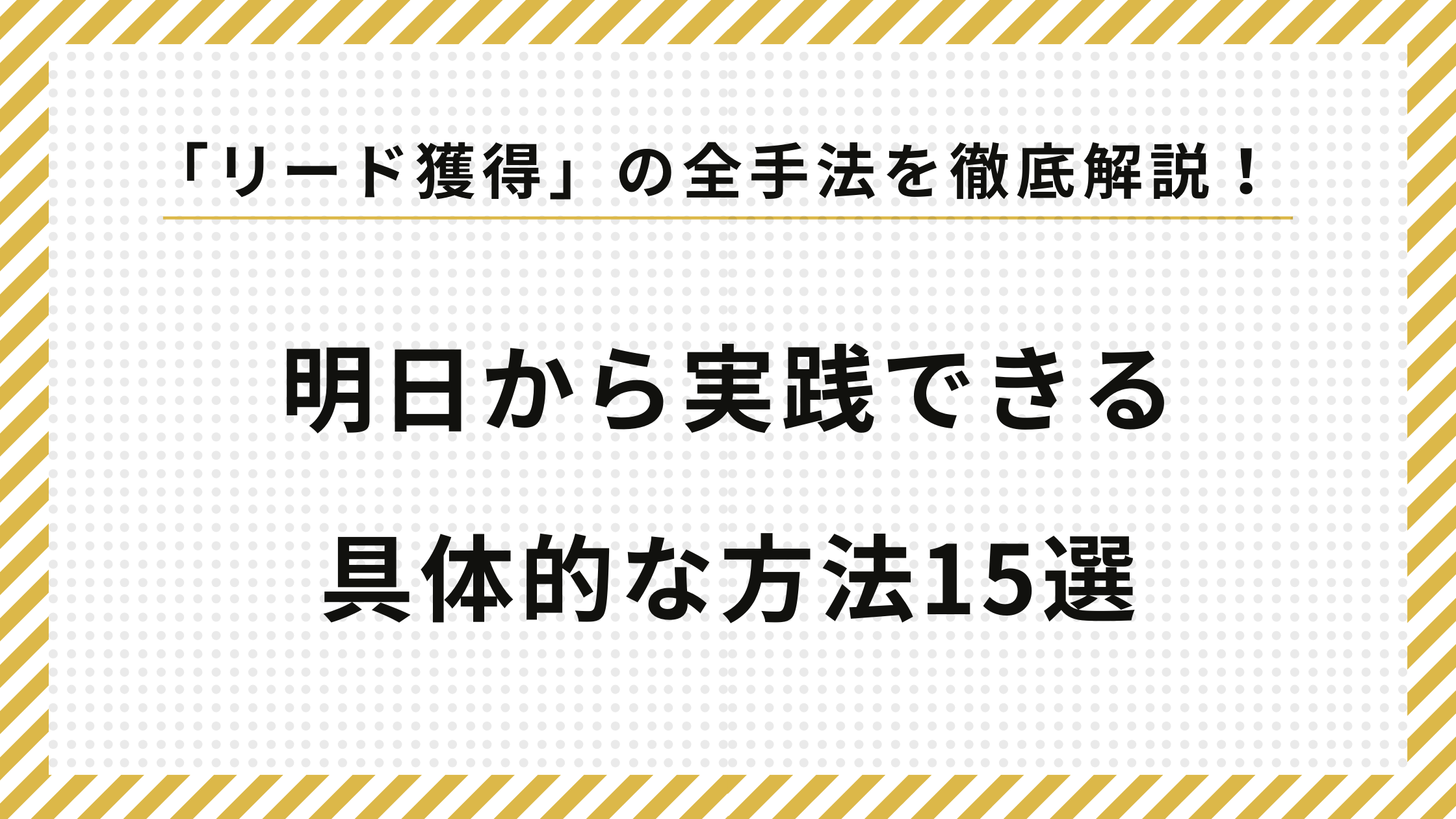
「リード獲得」の全手法を徹底解説!明日から実践できる具体的な方法15選
リード獲得
「新しい顧客を獲得したいけど、どうすればいいか分からない」
「Web広告や展示会など、色々試してはいるけれど、なかなか成果につながらない」
「そもそも、自社にはどんなリード獲得の方法が合っているんだろう?」
上記のような悩みを抱え、有効な打ち手を見つけられずにいる担当者の方も多いのではないでしょうか?
特に近年は、顧客の情報収集行動も多様化し、オンライン・オフライン問わず、さまざまなアプローチが存在します。選択肢が多いからこそ、「何から始めれば良いのか」「どの方法が自社にとって最適なのか」を見極めるのは簡単ではありません。
本記事では、現代のビジネスで有効なリード獲得の手法をオンライン・オフライン合わせて15種類、網羅的にご紹介。
それぞれの手法の有効性や成功のコツ、費用感まで「導入をイメージできる」レベルで詳しく解説していきます。
【一覧】一目でわかる!リード獲得の手法
以下の表では、各手法の特徴を比較しやすいように整理しています。
| 手法名 | 分類 | ターゲット | コスト | 始めやすさ | 効果期間 |
| 1. オウンドメディア(ブログ・SEO) | オンライン | BtoB/BtoC | 低 | △ | 中長期 |
| 2. Web広告 | オンライン | BtoB/BtoC | 中 | △ | 短期~ |
| 3. SNSマーケティング | オンライン | BtoC/BtoB | 低 | ◯ | 短期~ |
| 4. ウェビナー | オンライン | BtoB | 中 | △ | 短期~ |
| 5. ホワイトペーパー・資料ダウンロード | オンライン | BtoB | 中 | △ | 中期~ |
| 6. メールマーケティング | オンライン | BtoB/BtoC | 低 | ◯ | 短期~ |
| 7. Webメディア掲載・広告 | オンライン | BtoB/BtoC | 中 | △ | 短期~ |
| 8. プレスリリース | オンライン | BtoB/BtoC | 低 | ◯ | 短期~ |
| 9. 展示会・イベント出展 | オフライン | BtoB | 高 | × | 短期 |
| 10. セミナー(自社開催) | オフライン | BtoB | 中 | △ | 短期~ |
| 11. ダイレクトメール(DM) | オフライン | BtoB/BtoC | 中 | △ | 短期 |
| 12. テレアポ | オフライン | BtoB | 中 | △ | 短期 |
| 13. 新聞・雑誌広告 | オフライン | BtoC | 高 | × | 短期~ |
| 14. テレビCM・ラジオCM | オフライン | BtoC | 超高 | × | 短期~ |
| 15. 屋外広告・交通広告 (OOH) | オフライン | BtoC | 高 | × | 中期~ |
※始めやすさの目安:◯=比較的容易 / △=知識・準備が必要 / ×=難易度高・専門知識要
上記の一覧表を参考に、自社の状況や目的に合わせて、優先的に検討すべき手法の候補を考えてみてください。
そもそもリード獲得とは?
マーケティングや営業の文脈で使われる「リード」とは、単なる連絡先リストのことではありません。
リードとは、自社の商品やサービスに関心を示しており、将来的に顧客になる可能性のある「見込み顧客」の個人情報や企業情報のことを指します。
具体的には、以下のような情報がリードに該当します。
- Webサイトから資料をダウンロードした人の連絡先
- セミナーや展示会で交換した名刺情報
- メールマガジンに登録した人のメールアドレス
- Webサイトのお問い合わせフォームを送信した人の情報
ただし、一口に「リード」と言っても、その興味・関心の度合いはさまざまです。
たとえば、メルマガ登録者と、資料請求者では、後者の方がより導入に近い(=質の高いリード)と言えるでしょう。
【オンライン】Webを活用したリード獲得方法8選と実践ステップ
現代では、多くの人々が情報収集や比較検討をWeb上で行うのが当たり前になりました。そのため、オンラインチャネルを通じて見込み顧客と接点を持ち、リードを獲得することは、BtoB・BtoCを問わず、あらゆるビジネスにとって非常に重要です。
オンラインでのリード獲得には、以下のような特徴があります。
- データに基づいた効果測定と改善がしやすい
- ターゲットを絞ったアプローチが可能
- 比較的低コストから始められる手法も多い
- 時間や場所に縛られずアプローチできる
代表的なオンラインでのリード獲得方法として8つの施策を取り上げ、それぞれご紹介します。
1. オウンドメディア(ブログ・SEOコンテンツ)
オウンドメディアとは、企業が自社で所有・運営するブログやWebマガジン、導入事例ページなどの情報発信チャネルの総称です。
近年、広告に依存しない持続的なリード(見込み客)獲得の手法として、多くの企業がその価値に注目し、積極的に活用しています。
オウンドメディアがリード獲得に有効であることは、調査データによっても裏付けられています。[1]
株式会社宣伝会議が行った調査によると、オウンドメディアを運営している企業のうち「リード獲得の成果に結びつかない」という課題を感じている割合はわずか13.7%に過ぎませんでした。
これは、他の課題と比較して最も低い数値であり、多くの企業がリード獲得効果を実感していることの表れと言えるでしょう。
一方で、オウンドメディア運用には特有の難しさも存在します。前述の調査では、運営企業の約6割が「コンテンツ数の維持」を最大の課題として挙げています。
つまり、質の高いコンテンツを継続的に企画・制作し、公開し続ける体制を維持することに、多くの企業が苦労しているのです。
広告費が原則かからないというメリットがある反面、このコンテンツ制作には継続的な投資(時間、人的リソース、費用)が不可欠となります。
コンテンツ制作への投資が必要なため、特にオウンドメディア立ち上げ初期は、獲得できるリード数が少なく、CPA(リード獲得単価)が一時的に高くなる傾向があります。
しかし、これは先行投資と捉えるべきかもしれません。コンテンツが蓄積され、検索エンジンからの評価が高まるなどして軌道に乗れば、広告費をかけずに安定的にリードを獲得できるようになります。
その結果、中長期的にはCPAを大幅に引き下げることが可能になるのが、オウンドメディアの大きな魅力と言えるでしょう。
| 費用感 | サーバー代(月額500円~5000円程度)ドメイン代(年額1,000円~3,000円程度)記事作成を外注する場合、1記事あたり数万円以上 |
| メリット | 資産性が高いブランディング効果がある広告費をかけずに集客できる長期的に見るとリード獲得単価を抑えられる質の高いリードを獲得できる |
| デメリット | 時間がかかる継続的なリソース投入専門知識が必要検索アルゴリズム変動の影響 |
| 向いているケース | BtoB/BtoC 両方向き |
2. Web広告(リスティング広告・ディスプレイ広告など)
Web広告(インターネット広告)とは、検索エンジンの結果ページ、Webサイト、SNSなど、インターネット上のさまざまな場所に表示される広告全般を指します。
多くの企業、特にBtoBマーケティングにおいて、新規リード(見込み客)を獲得するための重要な手段として活用されています。
リード獲得を目的とする場合、主に以下のような種類の広告が用いられます。
- リスティング広告(検索連動型広告)
- ディスプレイ広告
- リターゲティング(リマーケティング)広告
これらの広告をクリックしたユーザーを、専用のランディングページ(LP)に誘導し、そこで資料請求や問い合わせ、購入などのアクション(コンバージョン)を促すことでリード獲得につなげます。
Web広告がリード獲得において有効な施策であることは、実際の企業の動向からも裏付けられています。
マーケティング調査機関「キーマケLab」がBtoB企業のマーケティング担当者を対象に実施した調査によると、2025年度のWeb広告予算を「増額予定(大幅・やや含む)」と回答した担当者のうち、実に55.8%がその最大の理由として「リード獲得効果が高いため」と回答しています。[2]
Web広告の費用(主にクリック単価/CPC)は、広告の種類、業界、競合、品質といった多くの要因によって、数十円から数千円以上と大きく変動します。
このようにWeb広告は仕組みが複雑なため、費用対効果を高めるには専門的な知識と運用ノウハウが欠かせません。 社内での運用には相応のリソース(時間・人・学習コスト)も必要です。
そのため、より確実に、効率よく成果を出したいのであれば、Web広告運用をプロに任せるのがおすすめです。
特に、戦略性が重視されるBtoBマーケティングにおいては、目標達成まで戦略立案から改善まで一貫してサポートしてくれる「伴走型」の専門家を選ぶと、より高い成果が期待できるでしょう。
| 費用感 | 月額数万円程度から比較的柔軟に設定可クリック単価は数十円~数千円以上と幅広く変動 |
| メリット | 即効性が高い高いターゲティング精度効果測定と改善の容易さ柔軟な予算設定 |
| デメリット | 継続的な費用発生運用ノウハウが必要広告疲れ・敬遠クリック単価の高騰 |
| 向いているケース | BtoB/BtoC 両方向き |
3. SNSマーケティング(アカウント運用・SNS広告)
SNSマーケティングとは、X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTokといったSNSプラットフォームを活用し、情報発信やユーザーとの交流(アカウント運用)、広告配信などを行うマーケティング手法です。
これにより、企業の認知度向上、Webサイトへのアクセス増加、イベント参加促進、あるいはDM(ダイレクトメッセージ)での問い合わせ対応などを通じて、リード獲得につなげることができます。
ビジネスマッチングサービス「比較ビズ」(https://www.biz.ne.jp) が、BtoB企業のSNS活用実態アンケートを行ったところ、企業のSNS活用について、「とても必要だと思う」と「必要だと思う」を合わせると、9割以上の企業が必要性を認識していることが明らかになりました。[3]
*比較ビズ(https://www.biz.ne.jp) をもとに自社で作成
また、同調査で活用している(または過去に活用していた)SNSツールを尋ねたところ、「Instagram」(52.5%)が最も多く、次いで「X(旧:Twitter)」(51.3%)と「Facebook」(51.3%)がほぼ同率で続く結果となりました。
*比較ビズ(https://www.biz.ne.jp) をもとに自社で作成
主な活用目的としては、「市場でのブランド認識向上」、「顧客との関係強化」、「製品やサービスの特性紹介」などが挙げられています。
SNSマーケティングは、BtoCにおいては主に商品の魅力発信、キャンペーン告知、ファンコミュニティ形成などに活用されます。
一方、BtoBにおいても、業界トレンドや専門知識、企業情報などの発信、ターゲティング広告に加え、顧客との関係を深めてCS(カスタマーサクセス)を向上させる上で重要です。
特にサブスクリプションモデルが主流の現代BtoBビジネスでは、顧客にサービスを継続利用してもらいLTV(顧客生涯価値)を最大化することが成功の鍵であり、そのためには顧客の成功を支援するCS活動が不可欠となります。
SNSは、有益な情報提供、活用事例の共有、ユーザーコミュニティ運営、迅速なサポートなどを通じて顧客との良好な関係を築き、効果的にCSを高めることができる有効なツールです。
| 費用感 | 企業アカウントの開設・運用自体は無料運用工数(人件費や外注費)が発生するSNS広告は1日数千円程度から出稿可能 |
| メリット | 高い拡散力ユーザーとの直接的な交流ファン化・エンゲージメント向上比較的低コストで開始可能精度の高いターゲティング広告 |
| デメリット | 炎上リスク継続的な運用工数成果が見えにくい場合もプラットフォームごとの特性理解 |
| 向いているケース | BtoB/BtoC 両方向き |
4. ウェビナー(オンラインセミナー)開催
ウェビナー(オンラインセミナー)とは、インターネットを通じてリアルタイムまたは録画で配信されるセミナー形式のイベントです。参加者は場所を選ばずにPCやスマートフォンからアクセスできます。
この手法では、参加申し込み時に氏名や連絡先などのリード情報を獲得します。さらに、セミナーの内容を通じて参加者の興味・関心を高め、終了後のアンケート回答、個別相談への申し込み、関連資料のダウンロードなどを促すことで、リード獲得だけでなく、既存リードの育成(ナーチャリング)にも効果を発揮します。
BtoBマーケティングに向いている方法で、専門知識の共有、製品・サービスのデモンストレーション、導入事例紹介、業界トレンドの解説などに適しており、特に重要性が高い手法です。
BtoB商材は機能や価格が複雑なことが多く、ウェビナーは視覚的なデモや詳細な解説を通じて、製品・サービスへの深い理解を促進します。
また、リアルタイムでの質疑応答は、顧客が抱える疑問や懸念をその場で解消し、納得感を高める絶好の機会となります。
これにより、企業や担当者への信頼感を醸成し、導入検討フェーズにおける意思決定を効果的に後押しすることができます。
さらに、終了後のアンケート結果や個別相談への申し込み状況から、関心度の高いリードを特定し、質の高い商談機会を創出することにもつながります。
| 費用感 | 配信ツール利用料(無料プラン~月数万円程度)集客コスト(広告費など:数万円~が目安)コンテンツ作成/講師準備工数(人件費/外注費)会場費不要でオフラインより低コストの場合あり |
| メリット | 広範囲から集客可能会場関連コストを削減できる録画データを再利用できる参加者データの取得・分析が容易質の高いリード獲得や育成に効果的 |
| デメリット | 参加者の集中を持続させることが難しい通信環境のトラブル双方向コミュニケーションの設計が重要テーマや告知によっては集客が難しい |
| 向いているケース | BtoB |
5. ホワイトペーパー(お役立ち資料)ダウンロード
ホワイトペーパーとは、BtoBマーケティングにおいて、ターゲット顧客が抱える課題解決に役立つ専門的な情報、ノウハウ、調査結果などをまとめた報告書(主にPDF形式)です
Webサイト上で公開し、ダウンロードと引き換えに氏名、会社名、メールアドレスなどの顧客情報を取得します。顧客は自ら「価値ある情報」を得るために個人情報を提供するため、課題意識や学習意欲の高い、質の高いリードを獲得しやすいのが特徴です。
ダウンロードされた資料の内容から、リードの興味・関心の対象を把握できます。
BtoBマーケティングにおいてホワイトペーパーは、リード獲得戦略の中核を担う非常に重要な手法です。
BtoBの購買プロセスでは、顧客は営業担当者に接触する前にオンラインで情報収集を行うことが一般的です。ホワイトペーパーは、購買プロセスの初期段階にある顧客に対し、詳細かつ専門的な情報を提供することで、顧客の自己学習を促進し、その後の商談を円滑に進めます。
また、特定の課題に関するホワイトペーパーのダウンロード行動は、その課題への強い関心を示すため、ダウンロード履歴を分析することで有望なリードを効率的に特定し、質の高いリードを選別する上で非常に有効です。
| 費用感 | 主なコストは資料作成リソース(人件費/外注費:数万円~数十万円以上)ダウンロード促進のための集客コスト(広告費など)も考慮 |
| メリット | 質の高いリードを獲得しやすい専門性・信頼性をアピールできる作成した資料がWeb上の資産となる営業活動にも活用できる |
| デメリット | 手間・時間・専門知識が必要ダウンロードされなければ効果がない情報の鮮度を保ちにくい |
| 向いているケース | BtoB |
6. メールマーケティング(メルマガ配信)
メールマーケティングは、獲得した見込み顧客(リード)や既存顧客のメールアドレスリストに対し、メールを配信することでコミュニケーションを図るマーケティング手法です。
セミナーやイベントへの誘導、商品・サービスの販売促進はもちろん、有益な情報を提供することで、顧客との長期的な関係構築・維持に役立ちます。
「SNS全盛期の現代で、メルマガはもう古いのでは?」そう考える方もいるかもしれません。しかし、メールマーケティングは顧客との良好な関係を築く上で、今も非常に有効な手段です。
実際、株式会社IDEATECHの調査によると、メルマガ配信によって多くの企業が成果を上げています。
出典:株式会社IDEATECH「リサピー®︎」
回答企業の59%が「Webサイト訪問者の増加」、54%が「自社認知度の向上」を実感していることが明らかになりました。[4]
Webサイト訪問者の増加は潜在顧客との接点を増やし、認知度の向上は自社への関心や信頼を高めます。これらが組み合わさることで、最終的に問い合わせや資料請求といった見込み客獲得(リード獲得)につながりやすくなるのです。
HubSpotのようなCRMツールを活用すれば、従来の一方的なメルマガ配信とは異なり、顧客一人ひとりとの関係性を深めるメールマーケティングが実現します。
顧客のWebサイト閲覧履歴、過去のやり取り、メールの開封状況といったデータを一元管理し、それぞれの関心や状況に合わせた最適な情報提供が可能です。
| 費用感 | メール配信ツールの利用料(月額無料プラン~数万円程度)配信コンテンツの作成工数(人件費/外注費) |
| メリット | 低コストで始めやすい費用対効果(ROI)が高いターゲットに合わせた情報配信が可能開封率、クリック率などの効果測定が容易MAツールを使えば自動化も可能 |
| デメリット | メールアドレスリストがなければ始まらない件名や内容によっては開封されずに埋もれる迷惑メール扱いされることもある |
| 向いているケース | BtoB/BtoC 両方向き |
7. Webメディア・業界サイトへの掲載・広告出稿
Webメディアや業界サイトへの広告掲載は、ニュースサイトや専門メディアなどに記事広告やバナー広告を出稿する手法です。
この方法の主なメリットは、特定の読者層に直接アプローチできることと、掲載メディアの信頼性を活用できることです。
最終的な目的は、これらの広告から自社サイトやLP(ランディングページ)へユーザーを誘導し、見込み客(リード)を獲得することにあります。
メディア掲載の戦略は、BtoCとBtoBで異なります。
BtoCでは、ライフスタイル誌やニュースサイトなどを通じて、広く認知を広げたり、特定の趣味・関心を持つ層に直接訴えかけたりします。
一方、BtoBでは、業界専門誌やビジネスメディアを選び、ターゲット企業の担当者・決裁者へ効率よく情報を届けることが重要です。これにより、専門知識や信頼性を効果的に伝えることができます。
どちらのケースでも、最適なメディアを選ぶことが成功の鍵となります。
| 費用感 | 掲載料(数万円~数百万円以上)記事やバナーなどの制作費 |
| メリット | 第三者メディアによる信頼性・権威性ターゲット読者層への直接的なアプローチブランディング効果SEO効果(質の高い被リンク獲得)につながる潜在層への認知拡大に有効 |
| デメリット | 掲載費用が高額になる場合がある効果測定が難しい場合がある適切なメディアを選定しないと効果が出ない広告色が強すぎると読者に敬遠される可能性がある掲載内容の自由度が低い場合がある |
| 向いているケース | BtoB/BtoC 両方向き |
8. プレスリリース配信
プレスリリースとは、企業が新商品、新規事業、イベントなどの新たな情報を、報道機関(メディア)へ公式に発表するための文書です。
主な目的は、ニュースとしてメディアに取り上げてもらい、記事や報道を通じて認知度や信頼性を高めることにあります。
リード獲得という点では、プレスリリース自体が直接多くのリードを生むことは稀です。しかし、メディア掲載によって企業の認知度や信頼性が高まれば、結果的に自社サイトへのアクセス増加や問い合わせにつながり、間接的にリード獲得へ貢献します。
特にBtoBにおいては、取引の判断材料となる「企業の信頼性」や「専門性」を示す上で、プレスリリースは非常に有効な手段です。
業界メディアやビジネス誌の担当者は常に新しい情報を求めており、プレスリリースは重要な情報源の一つ。これらのメディアに取り上げられることで、ターゲット企業の担当者や決裁者の目に触れる機会が格段に増え、質の高い問い合わせや商談につながる可能性が高まります。
| 費用感 | プレスリリース配信サービスの利用料(1回あたり無料~数万円程度が一般的)リリース文書の作成工数(人件費/外注費) |
| メリット | 高い信頼性広範な層への認知度向上低コストで始められるWebメディアに掲載されれば、SEO効果(被リンク獲得)も見込める企業の公式発表として信頼性を高める |
| デメリット | 必ずしもメディアに取り上げられるとは限らないニュース性のない情報では効果が薄い直接的なリード獲得効果は他の手法に比べて小さい情報の発表タイミングが重要になる |
| 向いているケース | BtoB |
【オフライン】対面や紙媒体も活用!リード獲得方法7選と実践ステップ
Webを活用したオンライン手法だけでなく、古くから行われているオフラインでのリード獲得も、依然として有効な手段です。
特に、直接顔を合わせることで、オンラインでは得難い信頼関係の構築や、深いコミュニケーションが可能になる場合があります。また、特定の地域や層にアプローチする際に効果的な手法もあります。
- 展示会・イベントへの出展
- セミナー(自社開催)
- ダイレクトメール(DM)送付
- テレアポ(テレマーケティング)
- 新聞・雑誌など紙媒体への広告掲載
- テレビCM・ラジオCM
代表的なオフラインでのリード獲得方法として、上記7つをご紹介します。
9. 展示会・イベントへの出展
展示会・イベント出展とは、特定のテーマや業界の催しに自社ブースを設け、製品デモ、ブランド認知向上、リード獲得、商談創出などを目的とする活動です。
ブース訪問者とは直接対話し、製品説明やデモを通じて興味の度合いをその場で把握できます。名刺交換やアンケートなどで獲得したリード情報は、後日のお礼メールや資料送付といったフォローアップに活用します。
展示会・イベント出典の最大のメリットは、多くの潜在顧客と短期間で直接的な接点を持てることです。
業界関係者が集まる専門的な展示会が多いため、特にBtoB企業のリード獲得戦略として重視されています。
| 費用感 | 高コストになる傾向(出展料、ブース設営・装飾費、輸送費、人件費、パンフレット・ノベルティ制作費など)数十万円~数百万円以上かかることも |
| メリット | 多数の潜在顧客と直接対面でコミュニケーションできる製品やサービスをその場で体験してもらえる競合他社の動向や業界トレンドを把握できるその場で具体的な商談につながる可能性がある企業の認知度やブランドイメージ向上 |
| デメリット | 費用が高額になりやすい準備に多大な手間と時間がかかる当日の運営に多くの人員が必要名刺情報の後日フォローが必須出展効果(費用対効果)の測定が難しい |
| 向いているケース | BtoB |
10. セミナー(自社開催)
ここで言うセミナーとは、企業が自らテーマを設定し、会場などを利用して対面形式で開催する説明会や勉強会を指します。オンライン形式は「ウェビナー」として別途解説しています。
主な目的は、専門知識を提供して参加者との信頼関係を築き、自社製品・サービスへの理解を深めてもらうことです。また、参加申込やアンケートを通じて、新規リードの獲得や既存リードの育成(ナーチャリング)にもつなげます。
参加申込時にリード情報を得る点はウェビナーと同様ですが、対面セミナーには特有のメリットがあります。参加者の反応を直接見ながら進行でき、質疑応答や懇親の場でより深いコミュニケーションが取れることです。これにより参加者の満足度が高まり、個別相談や具体的な商談へと発展しやすくなります。
専門的なテーマを扱うことが多いため、主にBtoBビジネスにおけるリード獲得・育成施策として有効です。ただし、投資やキャリア、趣味といったテーマであれば、BtoC向けにも十分に活用できます。
| 費用感 | 中コスト(会場費、集客のための広告費、資料印刷費、講師関連費(内製/外注)ウェビナーと比較すると費用は高くなる |
| メリット | 参加者と直接対面し、表情や反応を見ながらコミュニケーションできる質疑応答や懇親会などを通じて、深い関係性を構築しやすいその場で疑問点を解消でき、参加者の満足度を高めやすい企業のブランドイメージや信頼性の向上既存リードの育成(ナーチャリング)効果が高い |
| デメリット | 会場の手配や設営、当日の運営など、準備・実行に手間がかかる集客が重要であり、目標人数を集めるのが難しい参加できる人数が会場のキャパシティに依存する参加者は会場まで足を運ぶ必要がある天候や交通機関の乱れなどの外的要因に影響される可能性がある |
| 向いているケース | BtoB |
11. ダイレクトメール(DM)送付
ダイレクトメール(DM)とは、カタログや案内状といった印刷物を、特定の個人や企業に直接郵送するマーケティング手法です。
商品告知、イベント集客、資料請求促進、顧客との関係維持など、多様な目的で利用され、ハガキや封書など形式もさまざまです。
リード獲得においては、DMに記載したQRコードやURLからWebページへ誘導したり、同封の返信用はがきや電話番号で問い合わせを受け付けたりします。
成功の鍵は、送付ターゲットを明確にし、パーソナライズされた情報と開封したくなる魅力的なクリエイティブ(デザインやコピー)を用意すること、そしてリストの精度を高めることです。
DMは、BtoCでのセール案内や顧客への挨拶状、BtoBでの新サービス紹介やセミナー案内など、幅広い場面で活用されます。ターゲットリストの質とクリエイティブの内容が、その効果を大きく左右します。
| 費用感 | 中コスト(リスト購入費または作成費、デザイン・印刷費、郵送費)1通あたり数十円~数百円程度が目安 |
| メリット | ターゲットの手元に物理的な形で届けられるデザインや形状の自由度が高い五感に訴えるクリエイティブが可能Webをあまり利用しない層にもアプローチできる視認性が高いリストに基づきパーソナライズできる |
| デメリット | ターゲットリストが必要開封されずに捨てられてしまう可能性が高いコストが割高になる効果測定が難しい発送作業に手間と時間がかかる |
| 向いているケース | BtoB/BtoC 両方向き |
12. テレアポ(テレマーケティング)
テレアポ(テレマーケティング)とは、電話を通じて商品案内、商談アポイントの獲得、市場調査などを行うマーケティング手法です。
特に、まだ接点のない相手に電話し(アウトバウンドコール)、アポイント獲得を目指す活動を「テレアポ」と呼ぶのが一般的です。
リード獲得における主な目的は、直接的な商談アポイントを創出することです。電話での対話を通じて、相手のニーズをヒアリングしたり、見込み度合いを判断したりすることも可能で、アポイント情報やヒアリング内容がリード情報となります。
主にBtoBの新規顧客開拓で用いられますが、BtoCの一部(保険、不動産、通信サービス等)でも活用されます。成功には、質の高い架電リストの準備と、相手に話を聞いてもらうためのトークスクリプトや高度なコミュニケーションスキルが不可欠です。
| 費用感 | 中コスト(リスト購入費または作成費、電話通信費、オペレーターの人件費または外注費)固定報酬型や成果報酬型などがある |
| メリット | 相手の反応を確認できるニーズや課題などを直接ヒアリングできる短期間でアポイント獲得につながりやすい場所を選ばずに実施できる |
| デメリット | アポイント獲得率が低い傾向にある企業の評判を損なうリスクもある架電リストの質が成果を大きく左右するオペレーターのスキルや精神的な負担が大きい |
| 向いているケース | BtoB |
13. 新聞・雑誌など紙媒体への広告掲載
新聞・雑誌広告とは、新聞や雑誌の広告スペースに自社の商品やサービス情報を掲載する手法です。記事体裁の広告(編集タイアップ)や、デザインされた枠広告(純広告)といった形式があります。
リード獲得には、次のような方法が用いられます。
- 広告内に電話・FAX番号を載せて問い合わせを促す
- 資料請求用はがきを付ける
- QRコードやURLでWebサイト・LPへ誘導する
媒体自体が持つ信頼性やブランドイメージを活かしつつ、特定の読者層に情報を届けやすいのが特徴です。
どの媒体を選ぶかが重要で、BtoC向けには全国紙やファッション誌などでブランド認知度向上を図り、BtoB向けには業界紙や専門誌で特定の担当者・専門家にリーチし、リード獲得や製品理解を促すのが効果的です。
| 費用感 | 高コストになる傾向(広告サイズ、掲載ページにより大きく変動。数万円~数千万円以上と幅が広い)広告クリエイティブの制作費も別途必要 |
| メリット | 高い信頼性雑誌などは比較的高い精読率が期待できるWebにあまり触れない層にもリーチできる |
| デメリット | 掲載費用が高額になりやすい効果測定が難しい一度印刷されると内容の修正ができない若年層へのリーチが弱い掲載までに時間がかかる |
| 向いているケース | BtoB/BtoC 両方向き |
14. テレビCM・ラジオCM
テレビCM・ラジオCMは、それぞれテレビやラジオ番組の合間に放送される映像・音声広告です。マスメディアならではの広範なリーチと強い影響力を持ち、商品・サービスの認知度向上や企業・ブランドイメージ構築に大きな効果を発揮します。
直接的なリード獲得効果は限定的ですが、CMによる認知度向上がWebでの指名検索(会社名や商品名での検索)を増やし、サイトアクセス増を通じて間接的にリード獲得へ貢献します。「詳しくはWebで」といった検索誘導も一般的です。
また、CMを放映していること自体が、企業の信頼性を高める効果もあります。
非常に幅広い層に届くため、主に一般消費者を対象とするBtoCビジネスで活用されます。BtoBでは、タクシー広告や特定番組のスポンサーといった限定的な活用や、大企業のブランディング目的が中心となり、費用対効果の観点から実施のハードルは高い手法と言えるでしょう。
| 費用感 | 超高コスト(CM制作費と、放送料が非常に高額)実施には数百万~数億円規模の予算が必要 |
| メリット | 極めて広範な層へのリーチ圧倒的な認知度向上映像や音声などを活用できるブランドイメージを大幅に向上 |
| デメリット | 極めて高額であり、実施できる企業が限られるターゲットを細かく絞り込むことが難しい効果測定が非常に難しい |
| 向いているケース | BtoC |
15. 屋外広告・交通広告(OOH)
屋外広告・交通広告(OOH)とは、看板、デジタルサイネージ、駅や交通機関内の広告など、自宅外で接触する広告の総称です。主な目的は、特定の地域や交通機関の利用者に繰り返し情報を届け、企業や商品・サービスの認知度向上、あるいは地域でのブランド認知を図ることにあります。
広告を見てすぐのアクションにつながることは少なく、直接的なリード獲得効果は限定的です。しかし、特定エリアで繰り返し目にすることで認知度や親近感を高め、後日のWeb検索や来店といった行動を促す間接的な効果が期待できます。近年は、QRコードや検索窓のデザインを用いてWebサイトへ誘導する手法も増えています。
主に店舗を持つ地域密着型ビジネスや、広く一般消費者をターゲットとするBtoCで活用される手法です。BtoBにおいても、ビジネス街の主要駅や特定イベント会場周辺など、場所を絞ってターゲット層にアプローチする限定的な使われ方をします。
| 費用感 | 中~高コスト(数万円~数千万円以上と幅広い)広告物のデザイン・制作費も別途必要 |
| メリット | 反復効果が高い視覚的なインパクトが大きい一定の信頼感があるWeb広告を意図的に避ける層にもリーチできる |
| デメリット | ターゲットを細かく絞り込むことが難しい効果を直接測定するのが難しい屋外看板は天候による劣化や汚れの影響を受けるクリエイティブの自由度が限られる |
| 向いているケース | BtoC |
自社に合ったリード獲得方法を見つけるための比較・検討ステップ
やみくもに手法を試しても、時間やコストが無駄になってしまう可能性があります。成果を出すためには、自社の状況に合わせて最適な手法を選択し、集中して取り組むことが重要です。
- Step1:リード獲得の「目的」と「目標数値(KPI)」を明確にする
- Step2:ターゲット顧客(ペルソナ)を具体化する
- Step3:使える「予算」と「リソース(人員・時間)」を把握する
- Step4:各手法の特性(コスト、期間など)を理解し、比較検討する
ここでは、自社に合ったリード獲得方法を見つけるための具体的な比較・検討プロセスを、上記の4つのステップに分けて解説します。
Step1:リード獲得の「目的」と「目標数値(KPI)」を明確にする
まず最初に「何のためにリード獲得を行うのか?」という目的を明確にしましょう。目的が曖昧なままでは、どの手法が適切か判断できず、施策の効果を測ることもできません。
《目的の例》
- 新規の商談数を増やしたい
- 特定のサービスの問い合わせ件数を増やしたい
- Webサイトからの資料請求数を増やしたい
- メールマガジン購読者を増やしたい
目的が明確になったら、その達成度合いを測るための具体的な「目標数値」を設定することが重要です。特に、日々の活動や施策の進捗を管理し、改善につなげていくためには、KPI(重要業績評価指標) を設定することが効果的です。
KPIとは、最終的な目標(Goal)を達成するための中間的な指標のことです。リード獲得においては、以下のような指標がKPIとしてよく設定されます。
《KPIの例》
- Webサイトの月間アクセス(セッション)数:10,000件
- 特定ページの閲覧数(PV):1,500PV
- 資料ダウンロード数:月50件
- お問い合わせフォームからの送信数:月20件
- Web広告のクリック率(CTR):1.5%
- ウェビナーの申込者数(1回あたり):100人
- 展示会での名刺獲得数(1回あたり):300枚
企業の規模、業界、扱っている商材、施策の成熟度などによって、適切なKPIの目標値は大きく異なります。自社の過去のデータや業界平均などを参考に、現実的かつ達成可能な目標を設定することが重要です。
Step2:ターゲット顧客(ペルソナ)を具体化する
「誰に情報を届け、リードとして獲得したいのか?」というターゲット顧客像を具体的にします。ターゲットが曖昧だと、どのチャネルで、どのようなメッセージを発信すれば響くのかが分かりません。
ターゲット顧客像をより詳細に描いたものを「ペルソナ」と呼びます。ペルソナ設定では、BtoBとBtoCそれぞれの顧客の特性を理解し、以下のようにイメージします。
ペルソナを具体化することで、次のようなことが見えてきます。
- どのチャネル(Webサイト、SNS、展示会など)をよく利用するか
- どのような情報やメッセージに興味を持つか
- どのような課題やニーズを抱えているか
リード獲得の適切な手法選択や、効果的なコンテンツ・広告クリエイティブ作成の大きなヒントになります。
Step3:使える「予算」と「リソース(人員・時間)」を把握する
魅力的な手法が見つかっても、実行できなければ意味がありません。リード獲得にどれくらいの予算をかけられるか、そしてどれくらいの人員や時間を投入できるかというリソースを現実的に把握しましょう。
具体的には、以下の4つの観点について、自社の状況を整理してみましょう。
| リソースの種類 | 具体的な項目例 | 確認すべきこと |
| 予算 | 広告費ツール利用料外注費制作費印刷費 | 施策全体でどれくらいの費用をかけられるか? 各項目への配分は? |
| 人員 | 担当者の人数担当者のスキル・経験 | 必要な人数を確保できるか?担当者のスキルレベルは十分か? 教育は必要か? |
| 時間 | 準備期間実行期間効果測定の工数効果改善の工数 | 各フェーズでどれくらいの時間を確保できるか? 担当者の月間稼働時間は? |
| ノウハウ | 必要な知識・技術社内での過去の経験 | 社内に必要なノウハウ・経験はあるか? 不足分をどう補うか?(学習、外注) |
特に、オウンドメディア運用のように成果が出るまで時間がかかる手法や、展示会出展のようにまとまった費用と人員が必要な手法もあります。
自社の体力に見合った、現実的に継続可能な範囲で手法を選択することが大切です。
Step4:各手法の特性(コスト、期間など)を理解し、比較検討する
最後に、Step1〜3で明確になった自社の「目的・目標」「ターゲット」「予算・リソース」と、これまで紹介してきた各手法の特性を照らし合わせ、比較検討します。
それぞれの手法を比較検討する際には、次のような観点が大切です。
- 目的達成への貢献度:設定した目的・目標達成にどれくらい貢献しそうか?
- ターゲットへのリーチ: 設定したターゲット(ペルソナ)に、効果的にアプローチできるか?
- 予算との整合性:許容できる予算内で実施可能か?費用対効果は見込めそうか?
- リソースとの整合性:社内の人員、時間、ノウハウで実行・継続可能か?
- 効果が出るまでの期間:短期的な成果が必要か、中長期的な視点で取り組めるか?
また、必ずしも一つの手法に絞る必要はありません。目的やターゲットに合わせて、複数の手法を組み合わせる(施策ポートフォリオを組む)ことで、より効果的かつ安定的にリードを獲得できる場合もあります。
リード獲得の成功確率を高める!共通して押さえるべき3つのポイント
どの手法に取り組む際にも共通して重要となる、3つの基本的なポイントをご紹介します。
- 1.ターゲットに響く価値(オファー)を提供する
- 2. 次の行動を促す「CTA(Call to Action)」を設計・最適化する
- 3. 効果測定を行い、データに基づいて改善(PDCA)を続ける
これらを意識することで、リード獲得の「質」と「量」の向上につながります。
1.ターゲットに響く価値(オファー)を提供する
リードを獲得するということは、相手(見込み顧客)に個人情報や企業情報を提供してもらうということです。
相手が「この情報のためなら、自分の連絡先を提供しても良い」と思えるような、魅力的な「見返り(価値=オファー)」を用意することが非常に重要です。
オファーには、次のようなものが挙げられます。
- お役立ち資料(ダウンロードコンテンツ)
- セミナー・ウェビナー
- 無料相談・診断
- ツール・テンプレート
この「価値」は、設定したターゲット顧客(ペルソナ)が「欲しい」「役に立つ」「課題を解決してくれそう」と感じるものでなければなりません。
「自社が伝えたいこと」だけを押し付けるのではなく、「ターゲットが何を知りたいか、何に困っているか」という視点に立って、相手にとって本当に価値のある情報や体験を提供しましょう。
2. 次の行動を促す「CTA(Call to Action)」を設計・最適化する
ターゲットに響く価値(オファー)を用意したら、次はその価値を得るための具体的な行動を明確に促す必要があります。その役割を担うのがCTA(Call to Action:行動喚起)です。
CTAとは、Webサイト上のボタンやリンク、テキストなどで、ユーザーに取ってほしい行動を具体的に示すものです。CTAの例には、次のようなものが挙げられます。
- 「資料を無料でダウンロードする」
- 「ウェビナーに今すぐ申し込む」
- 「無料相談はこちら」
- 「お問い合わせフォームへ進む」
- 「メルマガに登録する」
CTAの文言やデザイン、配置場所によって、クリック率(=リード獲得率)は大きく変わります。A/Bテストなどを行い、どのCTAが最も効果的かデータを分析しながら、継続的に最適化していくことが重要です。
3. 効果測定を行い、データに基づいて改善(PDCA)を続ける
リード獲得施策は「やりっぱなし」では成果につながりません。必ず効果測定を行い、そのデータに基づいて改善を繰り返すことが不可欠です。この一連のサイクルをPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルと呼びます。
例えば、「Web広告のクリック率は高いが、資料ダウンロード数(KPI)が増えない」という状況なら、「広告の遷移先であるランディングページ(LP)の内容やフォームに問題があるのかもしれない」と考え、LPの改善を次の計画に盛り込む、といった具合です。
まずは設定したKPIを定期的にチェックし、小さな改善でも良いので継続的にPDCAサイクルを回していくという意識を持つことが、リード獲得の成功確率を着実に高めていきます。
BtoBリード獲得で特に意識したい点
ここまでの3つのポイントはBtoBとBtoC共通で重要ですが、特にBtoB(企業間取引) のリード獲得においては、加えて以下の点を意識すると良いでしょう。
- 信頼関係の構築
- 質の高い情報提供
- 長期的な視点
BtoBでは取引額が大きかったり、長期的な関係になったりすることが多いため、すぐに製品を売り込むのではなく、まずは専門知識を提供したり、課題解決に寄り添ったりすることで、企業としての信頼を得ることが重要です。
また、担当者は業務に関する課題解決のために情報収集をしています。断片的な情報ではなく、体系的で専門性の高い情報(ホワイトペーパー、調査レポート、詳細な事例など)を提供することが有効です。
さらに、BtoBは検討期間が長い傾向があります。一度接点を持ったリードに対して、すぐにアプローチするだけでなく、メールマーケティングなどを通じて継続的に関係を維持し、適切なタイミングで情報提供を行う(リードナーチャリング)視点が重要になります。
BtoBのリード獲得戦略について、さらに詳しい考え方や手法は以下の記事でも解説しているため、参考にしてください。
リード獲得後の重要プロセス
さまざまな手法を駆使してリード(見込み顧客)情報を獲得できたとしても、それで終わりではありません。リード獲得は、顧客との関係構築のスタート地点です。
獲得したリードの中には、すぐに商品やサービスを購入してくれる人もいれば、まだ情報収集段階の人、長期的に検討したいと考えている人もいます。
これらの多様なリードを実際の成果(受注や契約)につなげるためには、獲得後のプロセスが非常に重要になります。
リードナーチャリング(育成)
リードナーチャリングとは、獲得したリード(見込み顧客)に対して、継続的に有益な情報を提供したり、コミュニケーションを取ったりすることで、関係性を維持・深化させ、徐々に購買意欲を高めていくプロセスのことです。「顧客育成」とも訳されます。
獲得したリードのすべてが、すぐに商品やサービスを購入するわけではありません。多くのリードは、まだ検討の初期段階にいます。こうしたリードを放置してしまうと、競合他社に流れてしまったり、関心を失ってしまったりする可能性があります。
そこで、メールマガジンで役立つ情報を届けたり、限定セミナーへ招待したり、オウンドメディアの新しい記事を案内したりといった活動を通じて、時間をかけて顧客との関係を築き上げます。そして、顧客の検討が本格化した際に、自社を第一に想起してもらい、自然な流れで問い合わせにつながるような関係構築を目指します。
リードクオリフィケーション(選別)
育成されたリードの中から、購買意欲が十分に高まっており、受注につながりやすい有望な見込み顧客を選別するプロセスのことです。
営業担当者のリソース(時間や労力)には限りがあります。興味の薄いリードにまで手当たり次第アプローチしていては、非効率的であり、本当に有望なリードへの対応が手薄になってしまうかもしれません。
そこで、リードの属性情報(企業規模、役職など)や、これまでの行動履歴(Webサイトの閲覧ページ、メールの開封率、セミナーへの参加状況など)を基に、リードの「質」や「確度」を評価します。
例えば、特定の行動に対して点数を付ける「スコアリング」という手法が用いられることもあります。
この選別プロセスを経ることで、営業担当者は、より成約の可能性が高いホットなリードに優先的にアプローチできるようになり、営業活動の効率と成約率を大幅に向上させることが可能になります。
リード獲得を効率化・支援するツールの種類
リード獲得から育成、選別といった一連のプロセスは、手作業だけで行うには限界があります。特に、獲得するリード数が増えたり、実施する施策が多様化したりすると、管理が煩雑になり、効率も低下しがちです。
そこで活用したいのが、これらのマーケティング・営業活動を効率化し、より高度な分析や施策実行を可能にするための支援ツールです。代表的なツールには、次のようなものがあります。
- MA(マーケティングオートメーション)
- CRM(顧客関係管理)
- SFA(営業支援システム)
MAツールは、リード獲得から育成、選別までの一連のマーケティング活動を自動化・効率化するための多機能ツールです。
また、CRMは顧客情報を一元管理し、顧客との良好な関係を長期的に築くためのツールです。一方、SFAは営業活動そのものを支援し、効率化するためのツールです。
MAツールで獲得・育成したリード情報をCRM/SFAに連携させることで、マーケティングから営業まで一貫した顧客管理とスムーズな情報共有が実現します。
まとめ
リード獲得は、現代のビジネスにおいて不可欠な活動であり、完璧な計画を待つよりも、まずは自社に合った方法で「最初の一歩を踏み出すこと」、そして「継続的に改善していくこと」が、成果への一番の近道です。
そうは言っても「自社に最適な手法がどれか、まだ決めきれない」「具体的な施策の実行に不安がある、リソースが足りない」といったお悩みや課題を感じていらっしゃる方もいるかもしれません。
もし、リード獲得に関して専門家のサポートが必要だと感じられましたら、ぜひグロースパイロットにご相談ください。
グロースパイロットは、これまで多くのお客様のマーケティング・営業活動を支援し、リード獲得や売上向上に貢献してきた実績がございます。
貴社の状況や課題を丁寧にヒアリングし、最適なリード獲得プランのご提案から、施策の実行、ツールの効果的な活用まで、伴走しながらサポートいたします。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずは無料相談にて、貴社が抱える課題や目指したい姿について、お気軽にお聞かせください。
参考文献
[1]https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000541.000002888.html
[2]BtoB企業における2025年度Web広告予算の実態と展望に関する調査結果
[3]BtoB企業の93.4%が企業のSNS活用を「必要だと思う」と回答、活用ツールは1位がXで2位YouTube、3位Instagram|比較ビズ | 株式会社ワンズマインドのプレスリリース
